|
新年明けましておめでとうございます。早いもので、もう、そんなご挨拶をする年の初めになりました。歳を重ねるごとに時の流れが速くなると、諸先輩の方々がよくおっしゃるのを耳にしましたが、今まさに実感しております。本年も昨年同様宜しくお願い申し上げます。
さて、私の時間が瞬く間に過ぎてしまうように感じるには、それなりの理由があります。昨年、平成十五年は私にとりまして、人生での大きな転機を迎えた年でもあったからです。
平成十五年一月十日、私は、淀にある某病院の手術台の上に横たわっていました。病名は真珠腫性中耳炎。耳の中に出来る癌です。ほおって置くと耳内の組織を壊し、脳内に侵入し命取りになります。急ぎ、耳裏を切開し、腫瘍並びに膿を除去し、音系組織を形成するという手術を受けることになったのです。手術は二回に分けて行われ、一回目の除去手術に八時間を要しました。
ご承知のように、耳は、聴覚を司るのみならず、平衡感覚、味覚神経、顔面神経、さらに、皮一枚隔てて脳細胞と、人間が生きる上で重要な器官が集中しています。顕微鏡を使用しながらの細かい手術は、それだけで時間を必要としますが、担当医に言わせると、私の耳は大変酷い状態で、成熟していないのだそうです。振り返り考えてみると、子どもの頃から風邪をひいては、中耳炎になり、病院に行く。そんな繰り返しをよくしていました。膿が止まり、直ったかに見えた耳は、内耳に膿を溜め込み、腫瘍と化していたのです。もう少し発見が遅れれば命取りになるところでした。
この手術の二ヶ月前、私は、声の調子がおかしく、多少痛みもあるので、京大病院に通いました。診断の結果、仮声帯発声による炎症と言われました。つまり、声帯膜の外側の筋肉(仮声帯)が、何らかの理由で膜を塞ぎ、膜の振動を止めてしまうのです。発声の瞬間にこの症状が起こりますので、声が出ないということになります。これらは、声を使う仕事の方に多く見られる症状だそうで、疲労し擦れてきた声を無意識に修正しながら、発声し続けると、このような結果になるそうです。つまりは職業病といってもいいのかもしれません。とはいうものの、普段意識せずに出している声です。ましてや、仮声帯を動かさずに膜だけを震わし、発声するなど、考えもつきません。しかし、この症状を克服するには、ひたすら意識しながら発声訓練を積み重ねるしかないのです。まさに、ジレンマとの戦いです。そんな訓練を始めた矢先、右耳が全く聞こえなくなったのです。突然の症状に、当所は、ストレスから来る突発性難聴かと、勝手に自己診断していました。一難去って又一難、というよりは、一難来たりてもう一難。同じ京大病院の耳鼻科に駆け込んだところ、即、手術と診断。猶予が無いということで、京大担当医のもと、淀の病院での手術になったのです。まさにどん底に落とされた気分でした。
同時に二つの病を抱えつつ、それでも気持ちを奮い立たせ、前向きに考えてきた平成十五年十一月十四日、二回目の耳の手術を受けました。しかし、ここでも不運が訪れます。音系の形成手術のはずが、一回目の手術の腫瘍取り残しが見つかり、又除去手術のみになってしまったのです。と言うのも、この種の腫瘍・膿は僅かでも取り残しがあると、再発し広がるのです。この現象が真珠腫性中耳炎が耳の癌といわれる所以です。いずれにしましても、腫瘍膿の除去が完全に出来て、再発していないことが確認されないことには、第二段階の手術が出来ないようです。この手術が終われば・・・、一応耳の苦痛から開放されると思い込んでいたハヤル気持ちは、脆くも崩れ去りました。しかし、腐っていてもしようがありませんので、気を取り直し、こうなればじっくり腰を据えて病と闘っていこうと思います。
そんなこんなで、病に取り付かれた暗い昨年ではありますが、明るい転機の出来事もありました。一度挫折を経験しながらも嫁を迎えることが出来た上に、子どもまで授かることができましたことは、私にとりましてこの上ない悦びと同時に、大いなる励ましになりました。子どもは、「作る・作らない」ではなく「授かるもの」。ましてや、親が判断するのではなく、生まれてくる子どもが判断して、この親なら大丈夫と思い、この世に生まれ出る。と、ある高僧が言われていますが、親として信任を得て、授かった以上は、責任を感じております。
 |
 |
|
奥様(澄子さん)
|
藤田 阿澄(あずみ)ちゃん
|
その私事にも関わりませず、結婚並びに出産と、重ねてお祝いご厚情を賜りましたこと、この紙面を借りまして、厚く御礼申し上げます。
さてさて、今回の勝岳会だより巻頭ご挨拶は、頗る私の近況報告めいたダラダラとした文章になりましたが、お許しを願えればと存じます。
私的なことから一歩目を転じ、社会を見ますと、世上ではイラク派遣の問題、道路公団民営化の問題、郵政民営化の問題、少子高齢化と密接に関係している社会保障の問題等々、現在のこの時点での改革を少しでも誤れば、私たちの子どもや孫たちの生活を脅かしてしまうであろう問題が、次々と押し寄せて来ています。自動車メーカートヨタの奥田氏は、例え現時点で間違いの無い改革をしたとしても、経済が活性化し、成長していかなければ、これらの諸問題は悪循環に陥り、日本は急速な失速方向に陥るという主旨のことをものの本に書いておられましたが、まさしく、日本国は大きな転換期に来ていると見るべきでしょう。
ふざけている訳ではなく、水戸黄門の歌を想起してしまいます。「人生楽ありゃ、苦もあるさ・・・」。後に大きな楽を得ようと思うならば、やはりそれに匹敵する苦は付き物なのかもしれません。苦も楽しめるぐらいになれればいいのですが。皆様と共に励んで行きたいと思っております。
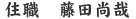
|